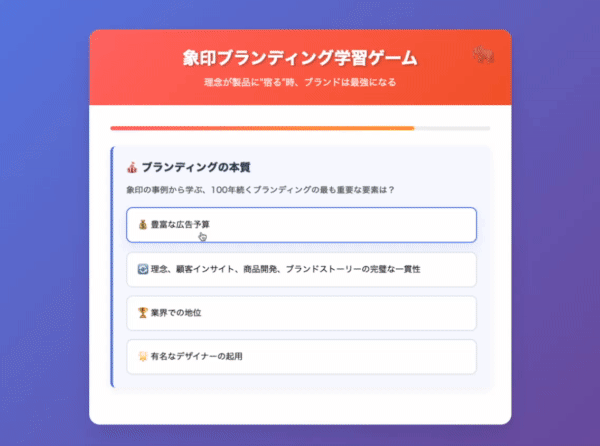企業の理念は、製品やサービスに正しく反映されていますか?象印の「パッキン一体型水筒」をケーススタディに、顧客インサイトを捉え、理念を製品に昇華させるブランディングの本質を解説します。
この記事は2025年7月1日にポッドキャストで配信した音声をもとに作成しています。ポッドキャストも合わせてお聞きください。
記事の一番下にはこの記事内容を深く理解できる簡単なゲームを掲載しています。ぜひ、遊んでみてください。
問い:あなたの会社の「理念」は、製品に“宿って”いますか?
多くの企業が、壁に立派な企業理念やビジョンを掲げています。しかし、その理念は、ショールームの展示品のように形骸化していないでしょうか。日々の業務に追われる社員にまで浸透し、生み出される製品やサービスの一つひとつに、その“魂”が宿っていると断言できるでしょうか。
理念と現場の間に横たわる深い溝。これは、多くの経営者や事業責任者が抱える根深い課題です。
もし、この溝を埋め、理念、顧客インサイト、商品開発、そしてブランドストーリーのすべてが完璧に一貫した企業があるとしたら、その戦略から学びたいと思いませんか?
その理想的なケーススタディが、日本の老舗メーカー「象印マホービン」にあります。同社のありふれた「水筒」という製品から、100年続くブランドの本質を紐解いていきましょう。
ケーススタディ:顧客の「不」を解消した革新的製品
きっかけは、ある一つの水筒でした。象印の「シームレスせん」搭載ステンレスボトル。
一見するとただの水筒ですが、この製品は、多くの消費者が長年抱えてきた「不」(不満・不便・不安)を、見事に解消しています。
-
「パッキンを分解して洗うのが面倒」という不満 → せん(蓋)とパッキンを一体化。「洗うのは2つのパーツだけ」という圧倒的な時短と利便性を実現。
-
「カバーがすぐに破れる、汚れる」という不便 → そもそもカバーを必要としない頑丈な設計とデザインの「カバーレス」モデルを開発。
これらは単なる機能改善ではありません。名もなき家事のストレスという、言語化されにくい顧客インサイトの的確な抽出と、それを解決する技術力の結晶です。この製品が、なぜ偶発的なヒットではなく、象印だからこそ生み出せた必然的なイノベーションなのか。その答えは、同社の揺るぎないブランド哲学にありました。
成功の源泉:理念を“動詞”にするブランド哲学
象印の成功の根幹には、創業時から変わらない企業理念があります。
-
企業理念:『暮らしをつくる』
-
コーポレートスローガン:『きょうを、だいじに。』
重要なのは、この理念が単なるお題目で終わっていないことです。象印にとって『暮らしをつくる』とは、顧客のリアルな生活を観察し、その中の課題を解決するという具体的な“動詞”なのです。
「パッキンが面倒」「カバーが破れる」という顧客の生々しい声(=暮らしの課題)を起点に、商品開発を行う。これは、まさに『暮らしをつくる』という理念の実践に他なりません。 製品が理念を体現し、理念が次の製品開発のコンパスとなる。この美しい循環こそが、象印ブランドの信頼性の源泉です。
象印の動画はこのコーポレートスローガンをうまく表現しています。
ブランドの原点:創業ストーリーに学ぶ「揺るぎないDNA」
この一貫した姿勢は、どこから来たのでしょうか。そのルーツは、100年以上前の創業物語に凝縮されています。
-
原点にある“作り手の情熱” 1918年、市川兄弟が「自分たちの手で魔法瓶を作りたい」という熱い想い一つで事業を開始。この「作りたい」という内発的な動機(パーパス)が、ブランドの最初のエネルギーとなりました。
-
困難を乗り越える“ビジョン” 下請け工場からメーカーへ、国内市場から海外市場へ。常に現状に甘んじることなく、より良い製品を、より多くの人へ届けたいという未来志向のビジョンが、会社を成長の軌道に乗せました。
-
世界観を込めた“商標” 海外展開を見据え、「家族を大切にし、生命力にあふれる『象』の姿が、人々の暮らしに寄り添う魔法瓶に重なる」として『象印』を商標に。これは、単なるマークではなく、自分たちの製品がどうあるべきかという世界観そのものを定義する行為でした。
この創業ストーリーは、単なる美談ではありません。
①強いパーパス、②明確なビジョン、③一貫した世界観という、現代のブランディングに不可欠な要素がすべて詰まった、まさにブランドの設計図なのです。
【経営者へ】象印から学ぶ、明日から活かすべき3つの教訓
象印の事例は、事業開発やリブランディングを考える私たちに、普遍的な教訓を与えてくれます。
-
イノベーションは「顧客の“不”」から生まれる
顧客満足(CS)を追求するあまり、潜在的な不満や不便を見過ごしていませんか?真のイノベーションの種は、顧客が口にする要望の中ではなく、彼らが諦めている「不」の中に眠っています。顧客の暮らしを顕微鏡で見るように観察し、その課題解決にこそリソースを集中させるべきです。
-
理念を「具体的な行動指針(動詞)」に翻訳せよ
あなたの会社の理念は、社員が明日からの行動を変えるための、具体的で分かりやすい言葉になっていますか?「社会に貢献する」という壮大な理念も、「まずはお客様の“面倒”を一つなくそう」という動詞に翻訳されて初めて、現場で力を発揮します。
-
「創業の情熱」こそが最強のブランド資産である
ブランドストーリーは、マーケティングのために後付けするものではありません。創業者の情熱、乗り越えた困難、製品名に込めた想い。その全てが、社員の誇りを醸成し、顧客を熱狂的なファンに変える唯一無二の資産です。今一度、自社の歴史を掘り起こし、その物語を語り継ぐ仕組みを構築してください。
象印が水筒を通して「暮らしをつくる」ように、あなたの会社は何を通して、顧客の、そして社会の「何」をつくりますか? その問いの答えこそが、100年先も色褪せない、強いブランドの礎となるはずです。
本記事の内容を簡単に楽しく学べるゲームを開発しました。ぜひ、遊んでみてください。ここから。