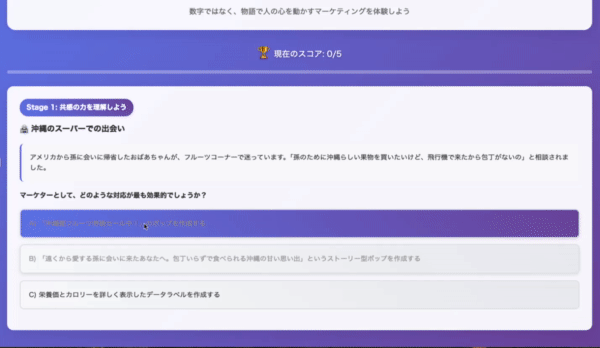マーケティングの本質は「数字」か「物語」か?沖縄の新テーマパーク「ジャングリア」への疑問から、人の心を本当に動かすものを探ります。データ重視の現代で、顧客との真の繋がりを築くためのヒントを、沖縄での心温まる実体験から解説。
この記事は2025年7月2日にポッドキャストにて配信した音声を元に作成しています。 Podcast も合わせてお聞きください。
この記事の内容を深く理解し、即実践できるようなゲームを開発しました。記事の下部に記載していますのでぜひ、遊んでみてください。
沖縄の新テーマパーク「ジャングリア」への違和感
今朝、X(旧Twitter)を開くと、沖縄のビジネスシーンを揺るがすニュースが目に飛び込んできました。沖縄北部に開業予定の巨大テーマパーク「ジャングリア」。その仕掛け人であり、USJをV字回復させた「マーケティングの神様」とも呼ばれる刀の森岡毅氏について、批判的な内容の特集が組まれていたのです。
私自身、その特集動画を全て見たわけではありませんが、コメント欄やSNSでは多くの批判的な意見が飛び交っていました。森岡氏が率いる株式会社刀からも、報道内容が偏っているとの公式発表が出る事態に。なぜ、これほどの実績を持つマーケターが、このような形で批判の対象となってしまうのでしょうか。
森岡氏の手法は、徹底的に数字とデータを分析し、科学的にマーケティング戦略を構築するものです。その力でUSJや西武園ゆうえんちを復活させた功績は、誰もが知るところです。しかし、その一方で、地元沖縄に住む私には、この「ジャングリア」プロジェクトに対して、周囲から期待やワクワク感がほとんど伝わってこない、という奇妙な現実がありました。
かつて沖縄にコストコがオープンした際は、開業前からあれほど大きな話題と熱気に包まれたのに、です。壮大なビジョンや巨額の投資、それらが語られる一方で、県民の多くはどこか他人事で、「また本土の頭のいい人たちが、自分たちのお金儲けのために何かやっている」という冷めた視線を送っているようにさえ感じます。この「温度差」こそが、現代のマーケティングが抱える根深い問題を象徴しているのかもしれません。
数字やデータだけでは、人の心は動かせない
森岡氏の著書を私も2冊ほど購入し、読んでみたことがあります。正直な感想を言うと、非常に難解でした。数学的、科学的なアプローチで市場を分析し、戦略を立てる。その緻密さと論理性の高さは理解できるものの、それが果たして「人の心」を動かす本質なのか、という疑問が拭えませんでした。
マーケティングとは、突き詰めれば「人の心を動かすこと」です。商品やサービスを通して、顧客に喜びや感動、共感といった感情を抱いてもらう営みのはずです。しかし、数字やデータはあくまで結果や予測を示すものであり、それ自体が感情を生み出すわけではありません。
人の心が動く瞬間とは、どんな時でしょうか。それは、誰かの語る物語に心を揺さぶられた時、困難を乗り越えた経験に共感した時、自分自身の過去の記憶がふと蘇った時ではないでしょうか。シミュレーションやデータ分析だけでは決して再現できない、一人ひとりの人生に根差した、生々しい感情の揺らぎ。それこそが、マーケティングが本来向き合うべき領域だと私は考えます。
沖縄県民が「ジャングリア」に熱狂できない理由も、ここにあるのかもしれません。プロジェクトの壮大さは伝わってきても、それが自分たちの生活や人生の物語とどう結びつくのか、その「接点」が見えないのです。これでは、どんなに科学的なアプローチを取ったとしても、真の応援ムードを醸成するのは難しいでしょう。
スーパーでの出会いが教えてくれた「物語」の力
先日、妻と近所のスーパー「かねひで」へ買い物に行った時のことです。フルーツコーナーで何を買おうか迷っていると、品のあるきれいな70代くらいのおばあちゃんに声をかけられました。
「ねえ、あなた。この『マンゴスチン』って、どんな果物なの?」
マンゴスチンガムでしか知らない私たちが戸惑っていると、おばあちゃんは次々と話しかけてきます。「沖縄にしかない果物はないの?」「この巨峰と小さいぶどうは何が違うの?」と。てっきり本土からの観光客かと思いきや、話を聞くと、なんとアメリカから今日着いたばかりの沖縄出身の方でした。
「孫のために、何か沖縄らしい果物を買ってあげたいの。でも、飛行機で来たから包丁がなくてね」
その一言で、彼女の行動の背景にある「物語」が見えました。遠いアメリカから、愛する孫に会うために故郷・沖縄へ帰ってきた(もしかしたら一緒にアメリカから来たかも知れません。理由は聞いていません)。そして、沖縄でしか味わえない特別なものを食べさせてあげたい、という優しい想い。私たちは一緒に、包丁がなくても食べられるぶどうが良いだろうか、メロンは切れないしな、と考え込みました。
しばらくすると、そのおばあちゃんが今度は「見て見て!」と興奮気味にゴーヤーを指さしました。「懐かしいわぁ」と目を細める彼女。私たちにとっては「最近、値段が高いな」くらいにしか思わないゴーヤーが、彼女にとっては、遠い過去の記憶や故郷の風景を呼び起こす、特別な「トリガー」になっていたのです。
この出来事は、私にマーケティングの重要なヒントを与えてくれました。商品は、単なる「モノ」ではありません。それは、人の人生や記憶と結びつき、特定の感情や物語を呼び起こす「きっかけ」になり得るのです。「アメリカ帰りのおばあちゃんへ。お孫さんと一緒に食べたい、懐かしの沖縄フルーツ」といったポップを添えるだけで、彼女の買い物体験は全く違う価値を持ったはずです。
ゼロから日本一へ。魂を揺さぶる経営者の実話
もう一つ、人の心を動かす「物語」の力について、深く考えさせられた出来事があります。先日参加した南部倫理法人会の経営者モーニングセミナーでのことです。
登壇されたのは、沖縄の老舗プレハブメーカー「カワバタハウス」の川畑 文夫社長。彼が、中部倫理法人会を立ち上げた時のエピソードは、まさに涙と笑いなくしては聞けない壮絶なものでした。
先輩から引き継いだセミナーの運営。引き継いだ当初、100人程度いた会員はどんどん減少して、最終的には会員はゼロ。講師を東京から高い旅費を払って招いているにもかかわらず、参加者はなんと自分一人だけ。気まずさのあまり「もう終わりにしましょうか」と講師に言うと、「何言ってるんだ!聞いているのは人間だけじゃない。天井も壁も床も聞いているんだぞ!俺はやる!」と一喝されたそうです。
そこから、毎週参加者ゼロのセミナーが続きました。彼は、たった一人の聴衆として、2歳の娘と奥様、そして奥様を介護するお母様を会場に連れてきました。幼い娘が泣き叫ぶ中、たった3人の家族のために、彼は必死にセミナーを続けたのです。
その苦しい時期が何年も続いた結果、一人、また一人と共感する仲間が増え、会員は10人、20人、100人と増えていきました。そしてついに、そのモーニングセミナーは参加者数で「日本一」になり、表彰されるまでに至ったのです。
この話を聞いて、会場の誰もが心を揺さぶられました。なぜなら、そこには理屈を超えた、一人の人間の「生き様」があったからです。苦労を乗り越えた経験談は、聞く者に「自分だったらどうだろうか」と当事者意識を抱かせ、深い共感を呼び起こします。これこそが、人の心を動かす「物語」の持つ、計り知れないパワーなのです。
これからのマーケティングは「一人」の物語に寄り添うこと
「ジャングリア」の話から、スーパーで出会ったおばあちゃん、そしてある経営者の壮絶な物語へ。一見バラバラに見えるこれらのエピソードは、全て一つの本質で繋がっています。それは、真のマーケティングとは、科学や数字で市場を分析することではなく、一人ひとりの顧客が持つ、かけがえのない「物語」に寄り添い、共感することである、ということです。
デジタル化が進み、あらゆるものがデータで分析できる時代だからこそ、私たち人間にしかできない価値提供が重要になります。それは、相手の経験してきたストーリーに耳を傾け、その記憶や感情を追体験する手助けをすること。
ゴーヤーを見て懐かしむおばあちゃんの過去に想いを馳せる。参加者ゼロでもセミナーを続けた社長の覚悟に心を震わせる。そうした人間的な共感の連鎖こそが、人を動かし、社会を動かし、そしてビジネスを動かす原動力となるのではないでしょうか。
科学的にマーケティングを設計することは、もちろん重要です。しかし、それだけでは、人の心に火を灯すことはできません。私たちが本当に向き合うべきは、データやグラフの奥にいる、「一人」の人間なのです。その人の人生に、物語に、どう寄り添うことができるのか。その問いこそが、これからの時代のマーケティングの出発点になるはずです。
ストーリーマーケティング体験ゲーム
数字ではなく、物語で人の心を動かすマーケティングを体験しよう。ゲームはここから。