もう3月も終盤ですね。年度末って、なんだか毎年バタバタしてるんですけど、同時に新しい季節に向けて「何か始めよう」って空気が漂っていて、僕は結構好きなんですよね。
で、ふと思ったんですけど——
今、AIってすごい勢いで進化してるじゃないですか?ChatGPTしかり、最近だとGoogleのNotebookLMとか。いろんなツールが出てきて、「これ、どう使えばいいんだろう?」って迷ってる人、実はめちゃくちゃ多いんじゃないかなって思ったんです。
でも、僕が思うに、いちばん変わるのは「教育」なんですよ。
この記事は2025年3月29日に Podcast にて配信した音声をベースに作成しています。 Podcast も合わせてお聞きください。
「教育」って、まだ旧時代のままじゃない?
新しいスタッフを迎える。 新卒を育てる。 マニュアルを作る。
この辺の“教育”って、結局まだ「OJT頼み」だったり、「先輩の背中を見て学べ」的な空気、残ってませんか?
もちろん、それが悪いとは言いません。でも、それだけだと効率悪すぎるし、属人化するし、何より人材が定着しない原因にもなってる気がするんです。
4月から新人スタッフが入ってくる
実際に僕の会社でも、4月から新しいスタッフが入ってきます。 で、オンボーディング(離陸支援)どうしよう?って考えていたときに、気づいたんですよね。
「あ、これAIでできるじゃん」って。
しかも、単に"できる"ってだけじゃなくて、めちゃくちゃ早くて、ラクで、効果的なんです。
AIで教育が変わる3つの理由
- 個人に合わせた学習ができる
- 動画や音声で感覚的に伝えられる
- データ化して何度でも使える
これ、すごくないですか?
Google Workspaceが最強の教育インフラだった件
最近いちばん感動したのが、Google Workspaceの2つの新機能です。
- NotebookLM(ノートブック・エルエム)
- Google Vids(グーグル・ヴィッツ)
まずNotebookLM、めっちゃすごい。
僕のポッドキャストを読み込ませたら、それを英語の自然な会話にしてくれて、しかも音声で出力してくれるんですよ。これそのまま英語教材にできるやん!って。
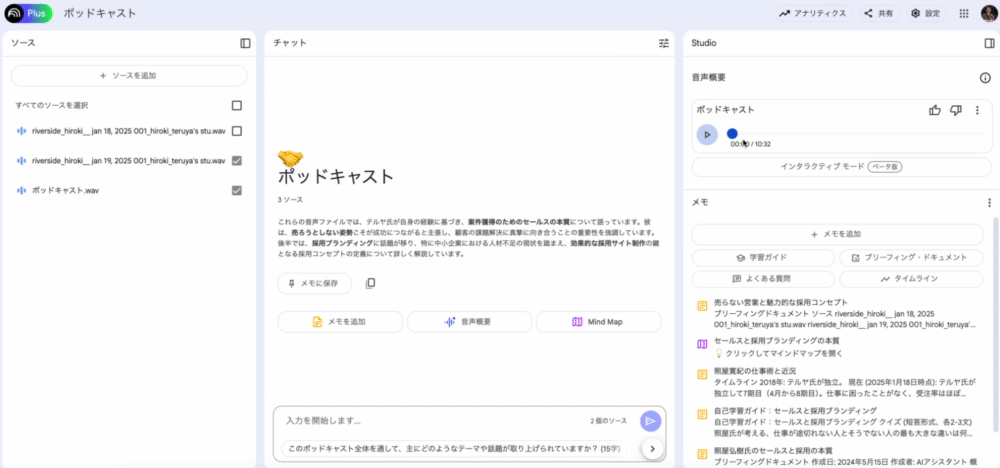
英語音声の一部(自動生成)
"Felt like you're hitting a wall when you're trying to get new clients..."
「新しいクライアントを取ろうとしても、壁にぶつかっているように感じたことはありませんか?」
これ、普通に海外向けにPodcast配信できますよね?
また、簡単にマインドマップも作成してくれます。
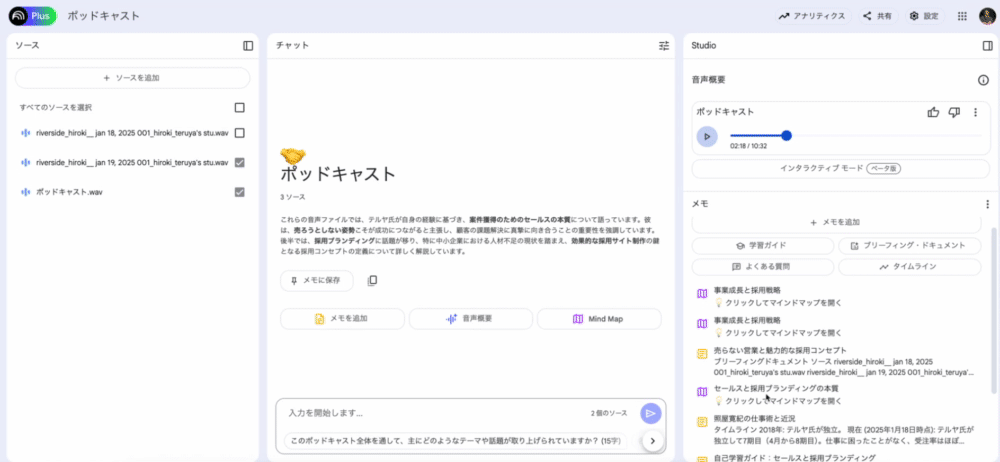
そしてGoogle Vids。これ、Googleスライドの感覚で、動画をサクッと録画・編集できるツール。 しかも、無料の素材を組み合わせたり、ナレーションを付けたりもできる。
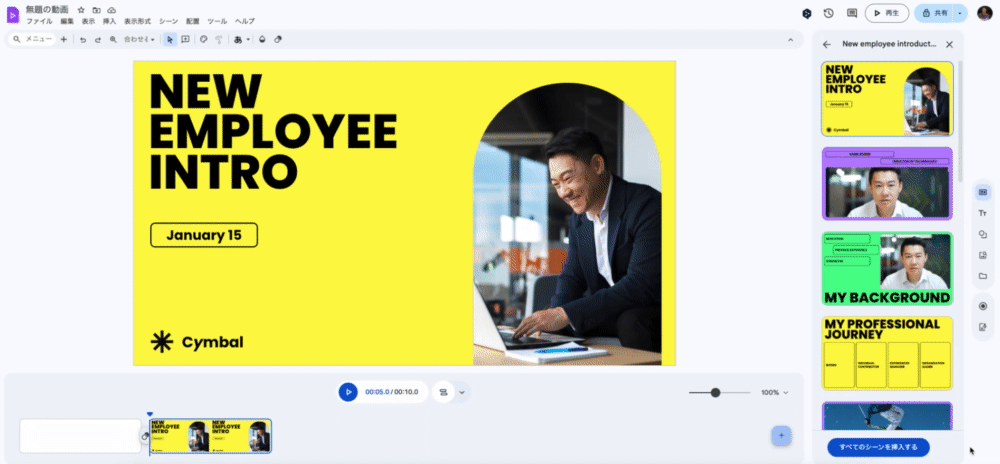
つまり、社内マニュアルとか操作説明とか、いちいちスライド作らなくても、動画で一発OKってことです。
動画マニュアルは“伝わるし、時短になる”
例えば、Wixでホームページを作ったあと、クライアントに「どうやって更新するの?」って聞かれること、よくあります。
以前はGoogleスライドにキャプチャ貼って説明してたんですけど、今は画面共有しながら喋るだけでOK。5分くらいで終わります。
これ、めちゃくちゃラク。
しかも一度作れば何度でも使えるし、スタッフが変わっても問題なし。
問題は「教育=人に頼る」思い込み
ここが一番のボトルネックだと思うんですよね。
教育って、「誰かが教えるもの」って思い込みすぎてて、そもそも仕組み化されてない会社が多すぎる。
でも今は、教育こそが自動化・データ化できる時代なんです。
氷河期世代・50代人材の採用も現実に?
最近、ハローワークで「氷河期世代向けの補助金ありますよ」って言われて驚きました。
要するに、「やる気はあるけどスキルがない人材」に対して、企業側が教育プログラムをちゃんと作れば補助金が出るんですね。
これ、AI教育を取り入れる企業にとってはめちゃくちゃチャンスだと思うんです。
教育は“知識”じゃなく“知恵”に進化する
最後に伝えたいのはこれ。
ただの情報やノウハウじゃなくて、「現場でどう使うか」「どう判断するか」っていう"知恵"に変換していくことが、これからの教育だと思ってます。
そして、そのためにはまず、今ある知識をデータ化・教材化しておくことが大事。
それができれば、AIが勝手に音声にしたり、動画にしたり、英語にしたりしてくれます。
これってもう、“教育革命”じゃないですか?
ということで、今日は「AI×教育革命」というテーマでお話してみました。
NotebookLMもGoogle Vidsも、ほんとにスゴいです。
「教育って、こんなにラクになるんだ」って体験、ぜひ一度してみてください。
そして、もし自社でもやってみたい!という方は、いつでもご相談くださいね。
それではまた!